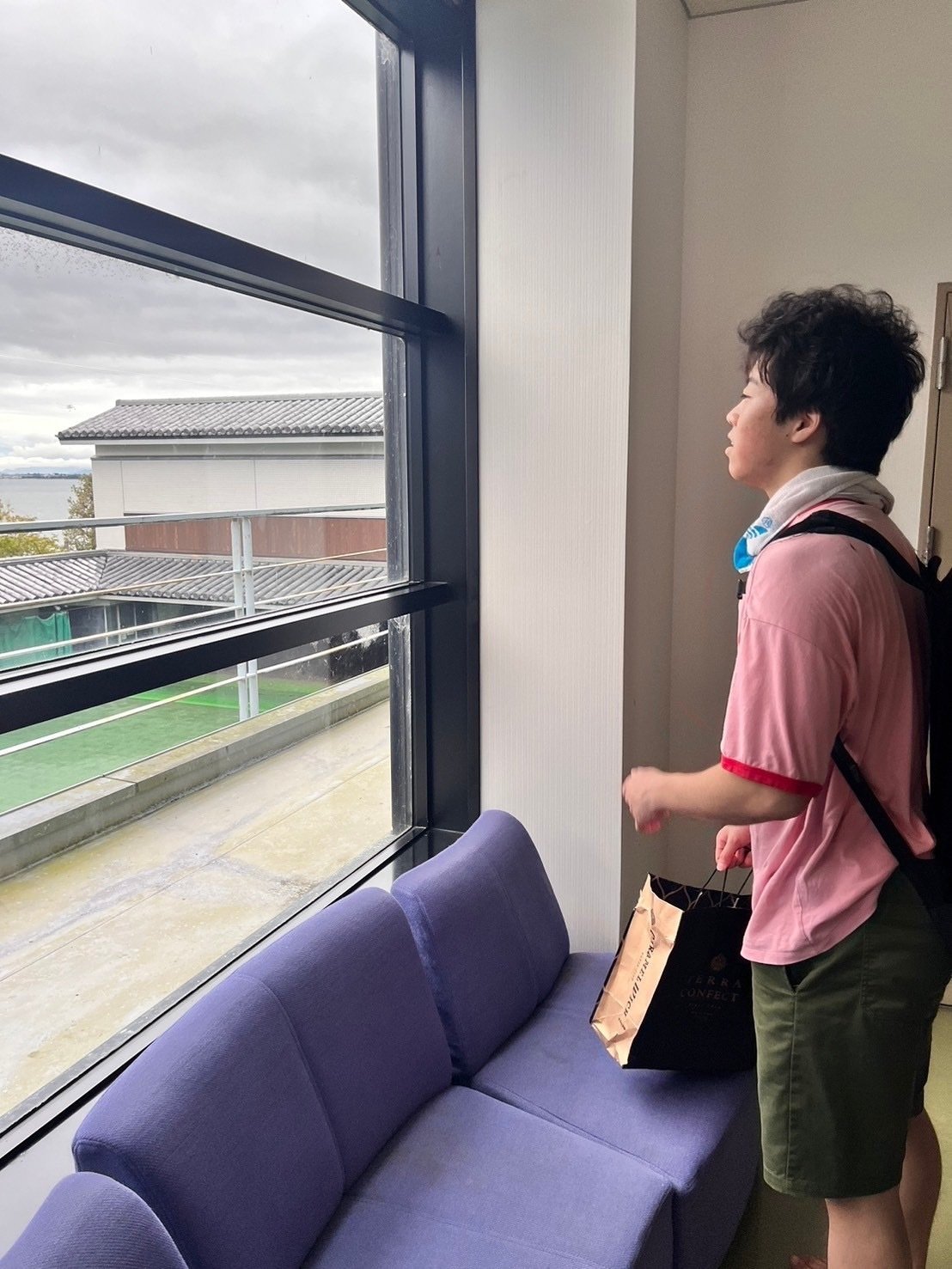お久しぶりです。一年生の渡邉です。今回は先日行われた一橋大学との定期戦について書かせていただきます。
一橋大学との定期戦は長い歴史を持ち,七大戦前に七大ルールで,そして今回のように三商戦前には三商ルールで試合を行います。私にとっては初めての三商ルールでの試合でとても緊張しました。周りの同級生,先輩方も貴重な対外試合に向けて,気合いの入った練習を積んで試合に臨みました。
試合では一進一退の攻防が繰り広げられました。私はというと,緊張こそしていたものの最近練習している巴投げを使うことができ,今後に向けた改善点も見つかりました。夏休み後の試合ということで,僅かながら持久力も以前よりついたように感じました。本戦後も親善試合をしていただき,さらに経験を積むことができました。部員全員が練習の成果を発揮し,また今後の改善点を得ることができた良い試合でした。
閉会式後には参加自由の乱取りを行い,応援に来てくださったOBの先輩方も参加してくださいました。一橋大学の皆さんと交流することができる良い時間を過ごすことができました。
一橋大学定期戦は終わりましたが,今後も2部大会,オープン大会などなど様々な試合が予定されています。それぞれの大会で良い結果を残すため,今後も精進を続けていきたいです。
最後になりますが,駒場まで足を運んで下さった一橋大学の皆様,応援に駆けつけて下さった関係者の皆様に感謝申し上げます。OB,OGの先輩方,今後もさらなる向上を目指して練習していきますので,お時間ありましたら道場で稽古をつけてくださりますと幸いです。
今回はここまでにさせていただきたいと思います。それではまた。
Tくん,この前はごめんなさい。
#年上彼女
ハロー。一年の阪上です。早く書けというT﨑の圧を感じるので今日はこの前行われた都公立についてかこうと思います。
団体戦は、一回戦の東京農工大に6対1で勝利、二回戦の一橋大学には3対3の内容差で勝利。決勝の学芸大にはフルマークで敗北という結果でした。特に印象深かったのは2対3の劣勢で迎えた一橋大学との大将戦での佐藤先輩の一本勝ちです。主務の仕事で、常日頃苦しんでいる佐藤さんの心からの笑顔を見ることができ、部員全員が自分のことのように喜んでいました。決勝は全敗という結果ではありましたが、何もできずに敗北という感じはしませんでした。T﨑もかなり戦えていました。来年は勝ちたい。

個人戦は、二度の鼻の骨折という悲劇のせいで松永さんが欠場、団体のメンバーは後の大会に向けて欠場という形で出場者が少なかったです。女子はメリッサさんが終始攻め続けて指導差で勝ちを納め、男子の無段の部では僕が優勝しました。めっちゃ嬉しい。形を面倒くさがらずに早く黒帯を取ろうと思います。同じ一年の永田、黒川も頑張っていました。
 目を瞑ってしまいました。申し訳ございません。
目を瞑ってしまいました。申し訳ございません。
他の個人戦に出ていた同期、先輩方も力を出し切り、全体的に収穫のあった大会でした。
今週末には一橋戦を控えているので、部員全員で万全の準備を期して臨めるように、残りの数日頑張っていきます。
最後に、初試合への準備を怠らずに行う一年永田の大きな背中で、この文章を締めます。アディオス!

こんにちは。3年の広羽です。
ブログを書くのは6ヶ月前の新歓ブログぶりです。
自分はもともとちょっとした感想文でさえ書くのが苦手で、どうでもいいリアペやLINEの返信にでさえも意味不明な長考をしてしまうことに悩んでいるのですが、新主将ブログを3ヶ月も溜めるような人間にはなりたくないのでさっさと書いてしまうことにします。
本題に入ると、寺田監督のご厚意で柔道部オリジナルのTシャツとポロシャツを制作しました。3年のメリッサがどちらのデザインも手がけ、制作手続きはOGの河本さんに担当していただきました。
 部T&ポロシャツ with メリッサ
部T&ポロシャツ with メリッサ
部Tは筋トレや道着のインナーとして、ポロシャツは大会の際に着用しています。
 国公立大会にて
国公立大会にてみんなでお揃いのポロシャツを着て観客席に座っているとまるで強豪校のようです。部員には、このポロシャツを普段着として使っている猛者もいるとか…
ポロシャツのデザインはとてもカッコいいので気に入っているのですが、唯一気になるのはこれを着ると自分の所属を主張しながら歩くことになってしまう点です。もし胸に「東京大学柔道部」とデカデカとプリントされた服を着ながら歩道をLUUPで爆走し、挙げ句の果てに警察にしょっぴかれる部員が出たらと思うと恐ろしいです。
部員の皆さんはこの服を着ている時は行動に気をつけてください。
最後になりますが、寺田監督、この度はTシャツ及びポロシャツ制作に御援助いただき誠にありがとうございました。大切にたくさん着させていただきます。
また、この2着はOB・OGの方々への販売が予定されています。今年度の赤門柔道をお送りする際、販売のお知らせも同封する予定ですので、ぜひ来年の七大戦観戦の際に着用いただければと思います。
皆様、お疲れ様でございます。1年の竹﨑です。今回は9/22,23に滋賀県立武道館にて行われた、七大学の合同練習会に参加してまいりましたので、そのことについてブログを書かせていただきます。実は、今回の元々のブログ担当は1年のWでしたが、彼は普段まるで仕事ができるかのように見せかけながら、何週間経っても投稿する気配すら見られませんでした。そのため今回は痺れを切らした私が黙って書こうと思います。こうすることで彼は私の言うことを聞かざるを得なくなるでしょう。どうしてもWの文章が読みたかったという方は、いつか将来のブログを懲罰として書かせようと思いますので、今しばらくお待ちください。
 見たことないフル装備
見たことないフル装備 京大戦に引き続いて行われたこの練習会は、東大柔道部にとっては夏練の集大成であり、また1年生にとっては初めて他大学の選手と練習することができる、非常に重要なイベントでした。選手各々は、前日の京大戦における完敗を受けたこともあり、強い気持ちを持って練習に臨んでいたことと思います。同じく1年のTAKAOは、七大戦での将来を考えて積極的に他大の1年生に当たりに行っていました。いつものことですが、彼の白帯詐欺っぷりは見ていて気持ちいいほどでした。彼こそまさに段級位制の欠陥であり、速やかな対処を求めたいです。というかTAKAOは早く黒帯を取得してください。他の1年生でも、習った技が成功した者がいたりと、非常に大きな収穫が得られた練習を行えたようです。私も、前日に完敗した者として様々なことを考えながら練習を行い、柔道スタイルの変革という課題を見出すことができました。
 研究
研究
練習に参加した2,3年の先輩方も同じように、色々な成長があった遠征、そして夏練だったのではないかと思います。この後も都公立大会や一橋戦と試合シーズンは続いていきますが、今後は京大戦のような悔しさは自分も含め誰も味わいたくないと思います。そのために先輩方や同期達もより一層頑張ると思うので、自分もその強さに食らいついて次こそは必ず勝ちに行きます。
そんなアツい合同練習でしたが一方で、夏練最後に行われた遠征ということもあってか、メンバーの疲労が溜まっていることが見られる場面が多かったと思います。宿舎に帰った某先輩の愚痴はいつも以上に冴えていたし、ある先輩は某Mぁつ永先輩をふんだんにイジることでストレスを発散しているようでした。(※もちろん松永さんは喜んでいました。)吉野さん(2年)も疲れていたせいか、たそがれていてかっこいい写真が激写されていました。
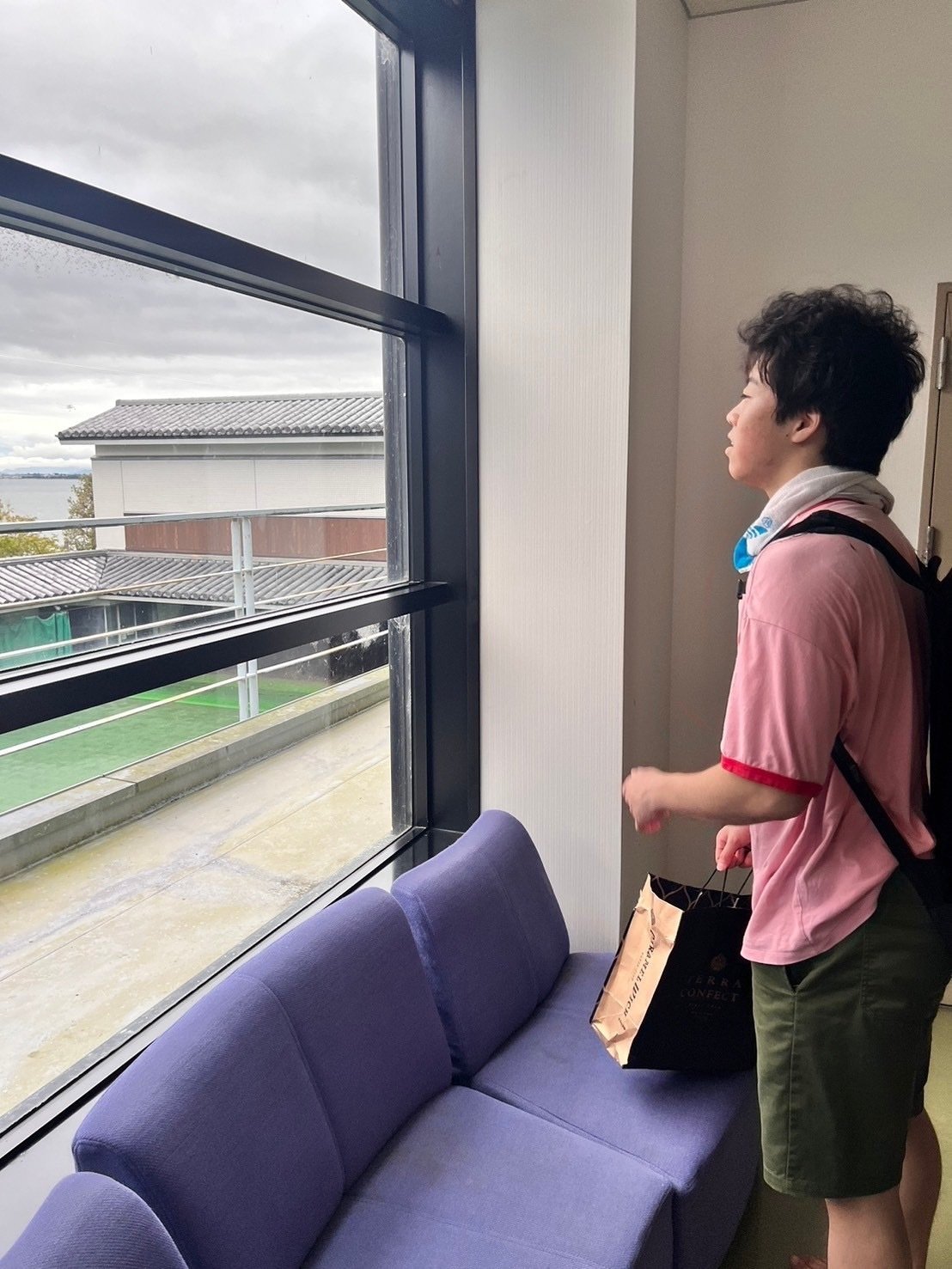 琵琶湖に想いを馳せるYさん
琵琶湖に想いを馳せるYさん 最後に、今回の京大戦・合同練習会でも、OB・OGの先輩方にご支援・応援を賜りました。また、一年生はカンパもいただきました。ありがとうございました。今後も引き続き、東大柔道部をよろしくお願いいたします。
余談ですが、合同練習会の期間中にKota先輩のご親族の方から差し入れをいただきました。とてもおいしかったです、ありがとうございました。残念ながら私は友人で浪人中の入道みたいなヤツに会いにいくため行くことができませんでしたが、練習後にすき焼きも振る舞っていただいたようです。最後に、すき焼きに誘われて満面の笑みを見せていた、みんなのアイドル1年Nを中心とした写真を以って、この文章を締めさせていただきます。

みなさんお久しぶりです。1年生の黒川です。先日、京都大学にて、東大・京大定期戦並びに親善試合を行いましたので、それについてのブログを書かせていただきます。
まずは東大・京大定期戦について。
勝敗と致しましては、残念ながら東大の完敗という結果に終わりました。大学初めの私の目から見ても、東大の選手にくらべ京大の選手は個としての能力が高く、たった数試合目にしただけで、日々練習する選手たちの息遣いまで聞こえてきました。柔道という競技の広さと深さを実感させられました。それが故に京大が、七大戦でなかなか良い成績を収められていないのが私は悔しい。15人のチームとしての力を競う七大戦では、人数が15人に満たない京大は不利です。京大は新歓にもっと注力すべきだ、と言うのは簡単ですが、身体を鍛え、技術を磨き、闘志を燃やしてきた選手たちが、競技とは別の面が原因で冠を手に出来ないのは、私はやはり納得できない。京大が七大戦で活躍する姿をいつか目にしたいです。
次は親善試合について。
この親善試合では、恥ずかしながら私も出場させていただきました。人生初の柔道の試合ということで、緊張するかなと思っていたのですが、予想よりも緊張せず、案外こんなもんか言うのが私の正直な感想です。全体といたしましては、多くの1年生が出場しました。誰もが自分に足りないものを知る良い機会になったと言っており、やはり本番に優る練習はないのだなと思いました。
最後になりますが、応援していただいた瀬戸口先輩、岡本先輩、神野先輩、新田先輩、伊藤秀高先輩、伊藤コウスケ先輩、ありがとうございました。